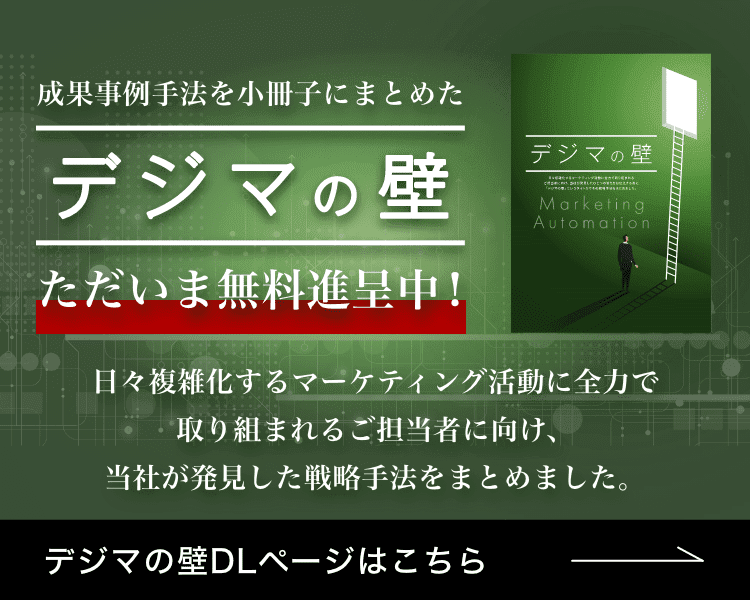第一章 情熱の雌伏
はじめの一歩
学校を卒業した私は、大手流通企業D社に入社が決まった。そして運良く販促担当として広告の仕事に携わることになった。当時、簡単に言えば販売促進が世の中のブーム。いわゆるクリエイターズブームである。日本でも「コピーライター」や「アートディレクター」というコトバが初めて社会的に認められてきて、糸井重里氏や浅羽克美氏などの人たちが、ノーネクタイでカッコ良く仕事をしている姿が脚光を浴びていた。私はそんなクリエイターへの憧れとともに、販促業界での第一歩を歩み始めることとなった。
しかし、せっかく大手流通の販促担当としてスタートをしたのも束の間、売場へ人事異動になってしまった。子供服や呉服、毛皮や宝石などといったあらゆる物をお客さまに売ってきたが、性格上どうも小売りという業種が向かず、現実と葛藤する日々が続いていた。いわゆる「待ち」の営業ができなかったからだ。
その当時のあるエピソードがある。社内で半年間の売上げを競う大会があった。私は見事MVPを獲ったのだが、実は店の呉服売場でお客さまを待ち構えていたのではなく、自分の車を使ってこっそり外商に出ていたのだ。D社グループでは外商は御法度。ある意味違反行為をして獲ったMVPには周囲からやっかみもあった。二十歳すぎの若者には、自分は成果を上げるための最善策をとったのに、一定のルールを盾にそれを許さなかった会社組織を理解できなかった。いま考えれば、会社としては「事故があってはならない」ということで決めていたルールだったろうから当たり前のことなのだが。
そんな出来事もあり、納得がいかない若い私は、D社を辞めて故郷の広島に帰ってくることになる。次はどんな仕事をしようかと悩んでいた際に、知人にたまたま教えてもらったのが15人ぐらいのD広告という広告代理店。大手紳士服の小売業A社をメインクライアントにしている会社だった。
広告のもつ素晴らしさへの期待と根拠のない自信を持ちつつ、私は明日から始まる新しい人生に胸を鳴らせながら故郷での再スタートを切った。
下積み時代
知人の紹介で広告代理店D広告の面接に行くと、面接に出てきたのは会社概要に記されていた社長ではなく、その夫人と別の役員であった。いきなり面接で「あんた元気そうだから入り」と言われ、その場で即合格。少し戸惑いながらも、その日は喜んで帰宅した。
数日後に初出社した私は、突然社長室に呼び出された。社長夫人と思っていた人は、実は夫から引き継いで社長を務めていると知ったのだが、同時に彼女は運転免許を持っていなかったために「今日からあんた運転手ね」と、これまた急に言われてしまった。
それから毎日毎日、女性社長の運転手としての日々。彼女は普通の営業先には行かず、毎日テレビ局をローテーションして廻っていた。当時の広告代理店はテレビ局に仕事を付けてもらっていたために、局に日参する方が売上げにつながるという構造だったのである。女性社長は地場老舗の会社を夫から引き継いだ人で、とにかくやり手だった。来る日も来る日もテレビ局ばかりローテーションして廻ってはどんどん仕事を獲っていくのだった。
社長が局で商談している間、待ち時間ばかりが長い運転手の私は、暇な時間を持て余して車中のラジオから流れる株式指標を聞いていた。それをきっかけに本を買って株の勉強をはじめて見よう見まねでやってみたら、なんと1年で60万の元手が600万になった。株で成功して当時の若者としては他が羨むほどの富を手に入れた私は、そのお金で外車を買ったり結婚資金を捻出したり、一人暮らしを始めたり・・・今振り返れば、何とも勝手気ままな生活をしていたものである。
しかし株は上手くいくものの、仕事の方は今回もさっぱりであった。流通業D社時代と同じく、広告代理店の古い慣習に苛まれたのだ。流通業D社時代も自分が成果を出そうと思うと社内のルールに阻止されたが、広告代理店にも古い業界慣習があって若造にはなかなか仕事をさせてもらえなかった。早くも入社半年で限界を感じた私は会社に辞表を提出した。すると「辞めてもらったら困る」という女性社長に退職理由を聞かれた。私が「営業がしたいからです」と言うと社長は、運転手を半分、営業を半分なら、と認めてくれて勤務継続が決まった。
営業に出てもいいと言われた私は、それからもう「必死」の一言。朝から晩まで新規飛び込み営業を徹底して行った。私の企画する提案をとにかくたくさんの人たちに見てもらいたかったから、この時はただただ、全力で取り組んでいた。